バスケの審判をやっていると、どこまでがディフェンスファウルで、どこからがオフェンスファウルなのかで悩むことが多いと思われます。
このことを明確に答えられる人は、どの位いるのでしょうか。
特に、社会人の遊びバスケレベルでやっていると、オフェンスファウルと判断されることがが極端に少ないのが現状です。
それは、次のようなことが原因かと思っています。
- そもそも基準が良く分からない。
- 自信がないので、ディフェンスファールにしておけば無難。
その結果、オフェンス主体の当たりの激しい当たりのゲームになってしまうことが多いように思います。
そこで、基本原則に立ち返ることで、オフェンスファウルとディフェンスファウルの境界線についての考え方を整理したいと思います。
ファウルの原則
ファウルを判断する基準としてまず教えられることに、
- 接触
- 責任
- 影響
があります。
接触
通常のファウル(テクニカルファウルは除く)はまず「接触」があったかどうか、が基準になります。
よく勘違いしている人が多いのですが、
「シュートする人のボールを上から押さえつけた」
という事象だけ捉えてファウルとする人がいます。
さらにこれがオフェンスプレーヤの背後から行ったとなるとファウルとされる可能性が一層高くなる傾向にあります。
そういう判断をする人の言い分としては、
「オフェンスプレイヤーのシリンダ領域を侵した」
というものです。
しかし、その時に体の接触がなかったとすれば、厳密にはファウルではないのです。
シリンダどうこう言う以前に体の接触があったのかどうか、これがファウルの大原則です。
責任
次に、「責任」です。
ここが、オフェンスファウルとディフェンスファウルの境目になります。
接触の責任がどちらにあったのか、を審判が判断します。
この部分がまさにシリンダの考え方となります。
バスケットボール競技規則(2015~)には、以下のように書かれています。
33.1 プレイヤーの位置とシリンダーの考え方
プレイヤーがコート上で普通に両足を開いて位置(ノーマル・バスケットボール・ポジション)を占めたとき、そのプレイヤーが占めている位置とその真上の空間をシリンダーという.
また、ディフェンス側のプレイヤーの責任については、以下の記述があります。
33.2 (3) 防御側プレイヤーが自分のシリンダー内でジャンプしたり手や腕を上に上げていて触れ合いが起こっても、そのプレイヤーに触れ合いの責任はなく、罰が科せられることはない.
33.3 正当な防御の位置(リーガル・ガーディング・ポジション)
(1)防御側プレイヤーが相手チームのプレイヤーに向かい合い、両足を普通に広げて床につけたとき、その防御側プレイヤーは最初の正当な防御の位置を占めたことになる.
(2)正当な防御の位置には真上の空間も含まれるので、真上の空間の内側であれば、まっすぐ上に手や腕を上げたり真上にジャンプしてもよい.
さらに、チャージングの定義に関する記述もあります。
33.4 (5) ・・・次の状態で触れ合いが起こった場合は、ボールをコントロールしているプレイヤーに触れ合いの責任がある。
①防御側プレイヤーが、ボールをコントロールしている相手チームのプレイヤーに向かって両足を床につけて最初の正当な防御の位置(リーガル・ガーディング・ポジション)を占めている.
②防御側プレイヤーが先に位置を占めていて、そのトルソー(胴体)に触れ合いが起こる.
つまり、オフェンスプレイヤーに正対して、正当な位置を占めているディフェンスプレイヤーに対する触れ合いの責任は、オフェンスプレイヤーにあるということです。
こうやって、読み返してみるとはっきりと書かれているんですね。
オフェンスファウルか、ディフェンスファウルかを判断する際には、まずは、これらの基準に立ち返ることが大切なのだと思います。
影響
最後に、その体の接触によって、プレーに影響があったのかどうかを判断します。
これは、オフェンス側かディフェンス側かに限らず、影響があったかどうかということです。
逆に言うと、影響がない接触はファウルにならないと言うことです。
バスケットボールのルールは、基本的にプレーヤ同士の接触を禁止するものとなっています。
しかし、ゴールに向かうオフェンス、それを阻止するディフェンス、それぞれがコート上を自由に動き回れるとなれば、接触は避けられません。
こういったプレイをすべてファウルとして捉えているとゲームの進行の妨げになりますし、なかなかゲームが進みません。
したがって、接触しても影響のないと審判が判断した場合には、見過ごしてもよいということになっているのです。
この「影響」は、完全に審判の主観ですので、この基準もファウルをあいまいにするポイントになっています。
自分は、大人バスケを見慣れていたので、ミニバスのゲームを見ているとちょっとした接触でもすぐにファウルが取られるのを見て、
「ちょっと厳しすぎない?」
と思っていました。しかし、
「子供の立場からすると、ちょっとした接触にプレーが影響されてしまうのです。」
というのを聞いて、「なるほどなぁ」と変に納得したのを覚えています。
原則に立ち返ることの重要性
ということで、オフェンスファウルの考え方について、バスケットボール競技規則の原則に立ち返って確認してきましたが、いかがでしたでしょうか。
新たな気づきを得た方も入れば、思っていたのとは違ったという人もいるでしょう。
特に、長年バスケをやってきた人たちは、自分の経験に基づいたルールを作り上げてきているので、なかなかもう一度ルールブックを読んでみよう、と考える人は少ないと思います。
しかし、あるときこの原則に立ち返ることで、自分の中で築き上げてきたルールとのズレを理解し、正しい方向に修正することができるのではないでしょうか。
最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。
バスケ315!
スポンサーリンク



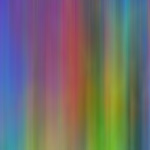







ファール
コメントいただき、ありがとうございます。
「ファウル」ではなく「ファール」の記載が正しいという意味でしょうか?
ルールブックを読んでいただければわかりますが、ルールブック上は「ファウル」と記載されています。